
今回の旅の舞台は、愛知県小牧市にそびえる小牧山城です。
かつて織田信長が初めて自ら築いた城として知られ、その歴史と遺構に触れたく、シニア夫婦二人で小牧山を訪れました。
戦国時代の風雲児・織田信長の原点とも言えるこの地で、初めて彼が築城した城の歴史を肌で感じてみたかったからです。
また、近年発掘調査で明らかになった石垣の技術や、その後の小牧・長久手の戦いにおける徳川家康との関わりなど、数々の歴史ドラマが詰まっている点にも大きな魅力を感じていました。
小牧山の山頂から広がる尾張平野の眺めも楽しみの一つでした。

私たちが実際に小牧山を訪れ、大手道をゆっくりと登り、小牧山歴史館で信長の築城とその後の歴史を学び、麓のれきしるこまきで発掘された貴重な資料や映像に触れ、
さらには小牧市役所の展望レストランで地元の方々のランチを味わうまでの旅の様子を、動画の流れに沿ってご紹介します。
この記事を読むことで、まるで私たちと一緒に小牧山を巡っているかのように小牧山城の魅力を追体験していただけるでしょう。
また、小牧山城へのアクセス方法や見どころ、歴史的な背景なども詳しく解説していますので、今後の旅の計画の参考にしていただければ幸いです。
小牧山へのアクセス:正面の顔、小牧市役所からスタート

小牧山城への訪問は、小牧市役所の駐車場を利用すると便利です。
小牧市役所の駐車場は終日開場しており、料金は無料で、294台の駐車が可能です。
市役所の所在地は、〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地です。
駐車場は小牧山の北側にもあり、そこは2時間まで無料で、その後30分ごとに200円となっています。
小牧山城の正面ルートとして知られる南側の大手道から山頂を目指します。

大手道は、お城の正門とされる「大手口」から山頂へと続く道(図中の赤色の道)のことで、織田信長が小牧山城を築城した際に整備されました。

小牧山資料館で頂いたパンフレット
この道を歩むことは、まさに織田信長の足跡をたどるロマンを感じさせてくれるでしょう。
大手道は階段も整備されていて、歩きやすく、自然を楽しみながら散策することができます。
10分から20分くらいで山頂へ到着です。
頂へ:小牧山歴史館で知る小牧城の歴史

小牧山への正面ルートである大手道を通り、小牧山頂上へ到着です。
山頂には、ひときわ目を引く小牧山歴史館(模擬天守閣)がそびえ立っています。
小牧山歴史館と麓の「れきしるこまき」では、ここでしか手に入らない「小牧山城 御城印」が販売されています。
御城印のデザインは織田版と徳川版の2種類があり、1枚あたり300円(税込)です。
小牧山を訪れた記念に、ぜひ手に入れたい一品です。
館内は織田信長が初めて自ら築いた城である小牧山城に関する展示に、令和5年4月1日に全館改装されました。
展示室では、小牧山城の歴史や、信長がこの地に城を築いた背景などを詳しく学ぶことができます。
特に目を引くのは、石垣についての発掘資料が詳しく展示されているコーナーです。
信長が築いた小牧山城では、土を盛り上げた土塁だけでなく、かなりの高さのある石垣が用いられました。
小牧山城の石垣は、小牧山がチャート層でできた岩山であるため、岩盤を切り崩した石をそのままの状態で使用した野面積みという工法で築かれています。
石を加工せず自然のまま積み上げる野面積みは、石と石の間に隙間ができるため、小さな間詰石が埋め込まれています。
また、巨石を支えるために、裏側には裏込め石が大量に出土していることも紹介されています。

発掘調査に関する展示では、2004年(平成16年)の調査で信長時代の巨石が発見されたこと、2013年(平成25年)には主郭部分を囲む3段の石垣が確認されたことなどが、写真や図面とともに解説されています。
これらの発掘成果を受け、2022年4月2日には、織田信長時代の石垣が復元されました。
展示されている「佐久間石」は、信長時代の石垣を証明する墨書が発見された貴重な巨石です。
小牧山の石垣には、地元のチャート層の岩山から切り出された石が使われており、まさに地産地消の城であったことがわかります。

織田信長の築城した小牧山については、築城の経緯や当時の状況などが詳しく解説されています。
1563年(永禄6年)、織田信長は清須から小牧山に居城を移しました。
当時、小牧山は美濃攻略の拠点として戦略的に重要な位置にあり、信長は城を築くと同時に、山の南側に城下町も整備しました。
しかし、信長が小牧山城に居住したのは短期間で、1567年(永禄10年)には岐阜城へ住まいを移したため、小牧山城はわずか4年で廃城となりました。
その後、小牧・長久手の戦い(1584年)では、徳川家康が小牧山城跡を改修して陣城としました。
歴史館の最上階からの眺めは、非常に広く、尾張平野を一望できる絶好の眺望地点となっています。
信長もこの景色を見て、天下統一への思いを馳せていたのかもしれません。
小牧山の麓へ:れきしるこまきで深める小牧山の記憶

小牧山頂の歴史館で小牧山城の概要を掴んだら、山を降りて麓にあるれきしるこまき(小牧山城史跡情報館)へ足を運びましょう。
この施設は、近年の発掘調査で明らかになった小牧山城の石垣や城下町、小牧・長久手の合戦などの歴史を、模型や映像を用いてわかりやすく紹介している、小牧山の記憶をより深く掘り下げるための重要な拠点です。
館内では、資料やスライドに加え、短い短編の解説映画などを通して、小牧山城の変遷や歴史的意義を学ぶことができます。
特に注目したいのは、信長時代の石垣を決定づける証拠となった「佐久間石」が展示されていることです。
また、小牧山城のジオラマは、当時の城の様子や城下町の広がりを具体的にイメージする上で非常に役立ちます。
発掘調査に関する展示も充実しており、信長が築いた石垣の特徴や、発掘された裏込め石、巨石などの貴重な資料を見ることができます。
これらの展示を通して、土の城が主流であった時代に、信長がいかに革新的な石垣を用いた城を築いたのか、その先見の明を感じることができるでしょう。
また、小牧・長久手の戦いにおける徳川家康による改修についても触れられており、両雄がこの地で繰り広げた戦いの駆け引きをより深く理解することができます。
徳川家康による土塁跡:小牧山の麓で見る往時の姿

資料館を出た後、小牧山の麓にある公園を散策すると、ちょうど桜まつりが終わり、提灯などの撤去作業が行われている様子が見られました。
春には多くの人が訪れるこの場所も、祭りの賑わいが過ぎ、静けさを取り戻していました。
公園の南側には、小牧・長久手の戦いの際に徳川家康によって築かれた土塁の跡が残っており、その断面が切り開かれ、強化プラスチックのようなもので覆われているのが観察できます。

これは、徳川家康が築いた土塁の構造を後世に伝えるための展示と考えられます。
高さ8mにも及ぶという南側の土塁は、復元されたものとしては日本最大級であり、当時の緊迫感を今に伝えています。
この断面を見ることで、土を盛り上げて築かれた土塁の内部構造を具体的に理解することができるでしょう。
お昼ご飯:市役所展望レストランでランチを味わう

小牧山の散策と資料館での学習を終えたら、お昼ご飯の時間です。
小牧山から麓へ下り、小牧市役所の展望レストランへ向かいました。
小牧市役所は、小牧山のすぐ南側です。
正面入口から建物に入り、エレベーターなどで展望レストランへ上がると、小牧山と小牧城が一望できる開放的な空間が広がっていることでしょう。

ここでは、市役所職員も利用するランチ定食を味わうことができます。
眼下に広がる景色を眺めながら、ゆっくりと食事をすることで、小牧の土地の魅力をさらに深く感じられるかもしれません。
小牧市役所の建物自体も、地域の行政の中心として市民に親しまれています。
展望レストランからの眺めは、小牧の街並みを把握する良い機会にもなるでしょう。
食後には、時間に余裕があれば、庁舎内を見学してみるのも良いかもしれません。
愛知県小牧市の小牧城(小牧山城)についてもっと詳しく

小牧城の概要
小牧城(小牧山城)は、愛知県小牧市の中央部に位置する標高85.9メートルの小牧山に築かれた城です。
この城は織田信長が初めて自ら築いた城として知られており、現在は史跡として整備され、小牧市のシンボルとなっています史跡小牧山。
小牧山は尾張平野の中に孤立した独立峰であり、総面積約21ヘクタールの小山です。
その地理的特性から頂上からは平野を一望できる絶好の眺望地点となっています小牧市。
歴史的背景

織田信長と小牧山城
小牧山城は1563年(永禄6年)に織田信長によって築かれました。
これは信長が初めて自らの手で築いた城であり、信長は清須から小牧山に居城を移しました。
当時、小牧山は美濃攻略の拠点として戦略的に重要な位置にありました。
信長は城を築くと同時に、山の南側に城下町も整備しました。
この城は石垣を多用する画期的な構造を持っており、現代の城郭施設の基礎となったとも言われています。
しかし、信長が小牧山城に居住したのは短期間で、1567年(永禄10年)に美濃の斎藤龍興を降し、稲葉山城(後の岐阜城)に住まいを移したため、小牧山城はわずか4年で廃城となりました。
小牧・長久手の合戦
その後、1582年(天正10年)に本能寺の変で信長が亡くなった後、1584年(天正12年)に「小牧・長久手の戦い」が起こります。
この戦いでは、織田信雄と徳川家康の連合軍が小牧山城跡を改修して陣城とし、豊臣(羽柴)秀吉軍と対峙しました。
徳川家康は一万五千の兵を率いて織田信雄軍と合流し、小牧山を本陣として秀吉に対抗しましたが、小牧付近では大きな戦いは行われず、同年11月に秀吉と信雄が和睦し、家康も秀吉と和解したため、再び廃城となりました。
江戸時代以降
江戸時代になると、小牧山は尾張徳川家の所領となり、徳川家康ゆかりの地として保護されました。
城下町の一部は移転し、史跡として保存されるようになりました。
明治時代以降は、公園化や施設の移築、寄贈などの変遷を経て、今日では史跡として整備・管理されています。
現在は山全体が史跡に指定され、戦国時代の遺構が良好な状態で維持されています。
現在の小牧山と観光情報

施設概要:現在の小牧山には主に2つの施設があり
小牧山歴史館
山頂に位置し、模擬天守閣のような外観を持ちます。
令和5年4月1日にリニューアルオープンし、戦国時代の小牧山に関する展示に全館改装されました。
- 開館時間:午前9時~午後4時30分(有料エリアへの入場は午後4時15分まで)
- 入場料:大人200円(団体30人以上は100円)、18歳以下無料
れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)
山麓に位置し、近年の発掘調査で明らかになった小牧山城の石垣や城下町、小牧・長久手の合戦などの歴史を、模型や映像を用いてわかりやすく紹介しています。
- 開館時間:午前9時~午後5時(常設展示室への入場は午後4時30分まで)
- 入場料:大人200円(団体30人以上は100円)、18歳以下無料
※どちらかの施設の入場料を支払えば、もう一方の施設にも入場できます。
アクセス方法
電車でのアクセス
名古屋駅から地下鉄・名鉄小牧線を利用し小牧駅へ
- 地下鉄名古屋駅(東山線)→ 栄駅(名城線)→ 平安通駅(上飯田線・名鉄小牧線)→ 小牧駅
- 地下鉄名古屋駅(桜通線)→ 久屋大通駅(名城線)→ 平安通駅(上飯田線・名鉄小牧線)→ 小牧駅
- 小牧駅からは西へ徒歩約20分(1.9km)、またはバスを利用
名鉄犬山線経由
- 名鉄名古屋駅(名鉄犬山方面行き)→ 岩倉駅
- 岩倉駅東口バス乗り場から名鉄バス小牧駅行(小牧市役所経由)に乗り換え、小牧市役所前下車
バスでのアクセス
名鉄バスセンター、伏見町、錦通本町及び栄(オアシス21)から高速バス(近距離高速線 桃花台)に乗車、小牧市役所前で下車
車でのアクセス
小牧ICより国道41号を南下し、弥生町交差点を東へ約5分
見どころ
- 石垣遺構:織田信長が築いた時代の石垣が発掘調査により明らかになっており、その建築技法や保存状態を確認できます。
- 城下町跡:発掘調査により、信長が整備した城下町の跡が発見されており、当時の生活や文化を知る手がかりとなっています。
- 豊かな自然:春の桜、夏の青葉、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季折々の美しい自然を楽しむことができます。特に桜の季節には「小牧山さくらまつり」が開催されます。
- 眺望:山頂からは尾張平野を一望できる絶好のビューポイントとなっています。
小牧山の文化的・歴史的意義
小牧山は単なる観光スポットではなく、日本の戦国時代を象徴する重要な史跡です。
特に、織田信長が初めて自ら築いた城であることや、小牧・長久手の戦いの舞台となったことから、歴史的価値が高く評価されています。
また、小牧山の遺構は良好な状態で保存されており、現代の私たちが戦国時代の城郭構造や軍事技術を学ぶ貴重な資料となっています。
さらに、市民の憩いの場としても愛され、小牧市のシンボルとして地域のアイデンティティ形成にも重要な役割を果たしています。
歴史的背景から現在の観光情報まで、小牧城の多様な側面についてまとめました。
織田信長の歴史的足跡を辿るとともに、現代においても魅力的な文化遺産として親しまれていることがわかります。
旅の終わり:名古屋へ
小牧山での歴史探訪を終え、私たちは名古屋へと帰路につきました。
今回の小牧山城の旅は、戦国時代の重要な舞台となったこの地の歴史と魅力を深く知る貴重な機会となりました。
今回の旅を振り返ると、まず印象的だったのは、織田信長が初めて自ら築いた小牧山城の歴史とその革新的な石垣です。
土の城が主流だった時代に、信長は早くから石垣を用いた築城を行った。特に小牧山城の石垣は、自然の岩盤を活かした野面積みという独特の工法で築かれており、その粗野でありながら堅牢な美しさは、後の近世城郭の礎を築いたと言えるでしょう。
れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)では、「佐久間石」をはじめとする発掘資料を通して、信長時代の石垣について深く学ぶことができました。
また、小牧山は1584年(天正12年)の小牧・長久手の戦いにおいて、徳川家康が陣を置いた重要な場所でもあります。
山麓に残る家康が築かせた土塁の跡は、高さ8mにも及ぶ日本最大級の復元土塁であり、当時の緊張感を今に伝えています。
小牧山全体が、信長と家康という二人の天下人の足跡を色濃く残す場所であることを改めて実感しました。
小牧山頂からは、濃尾平野を一望できる絶景が広がっていました。信長もこの景色を眺めながら、天下統一の夢を抱いていたのかもしれません。
そして、山麓のれきしるこまきでは、発掘調査の成果や城下町の様子などが分かりやすく展示されており、小牧山城の歴史を多角的に理解することができました。
今回の小牧山城への旅を通じて、日本の歴史の奥深さを改めて感じることができました。
スポンサーリンク

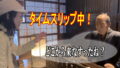

コメント